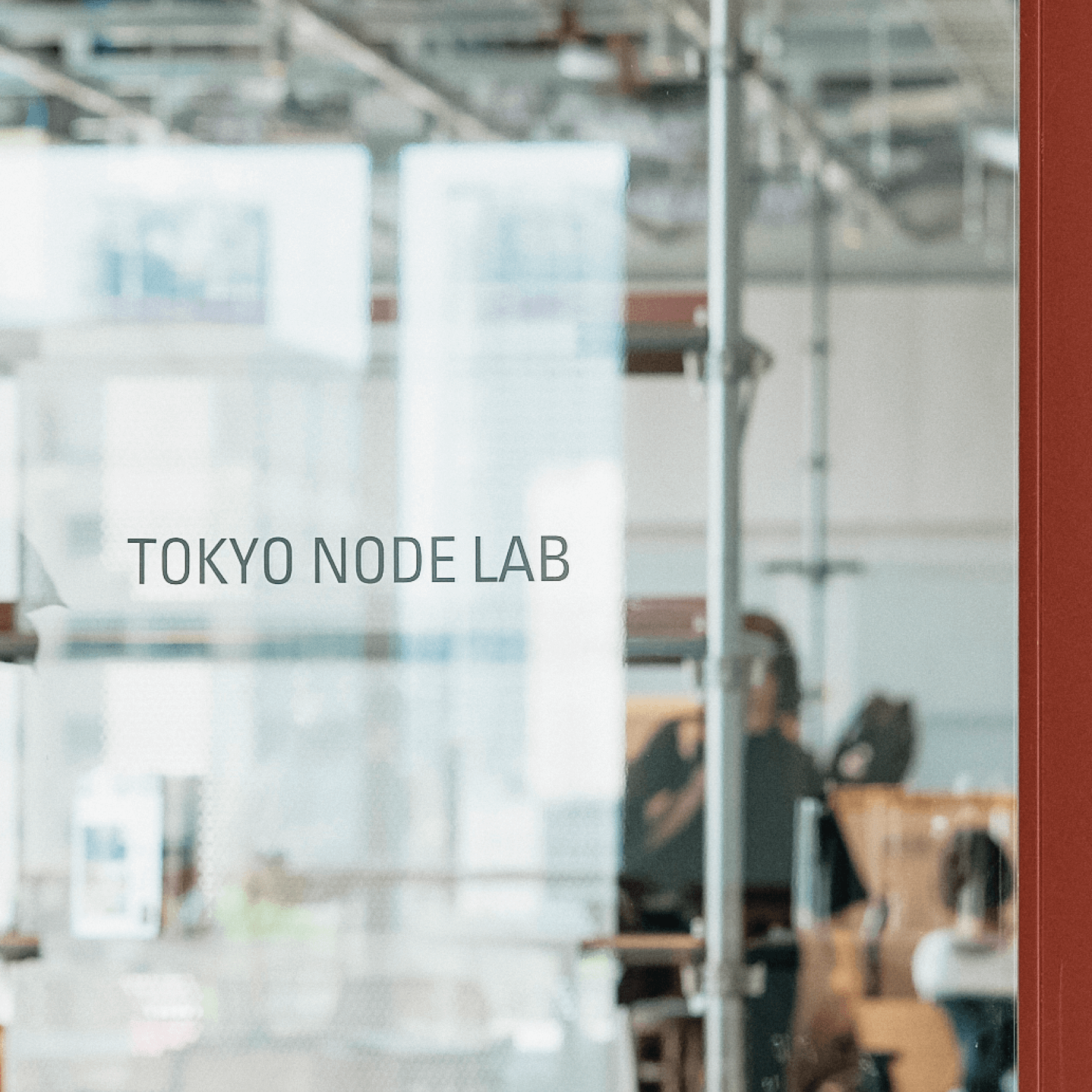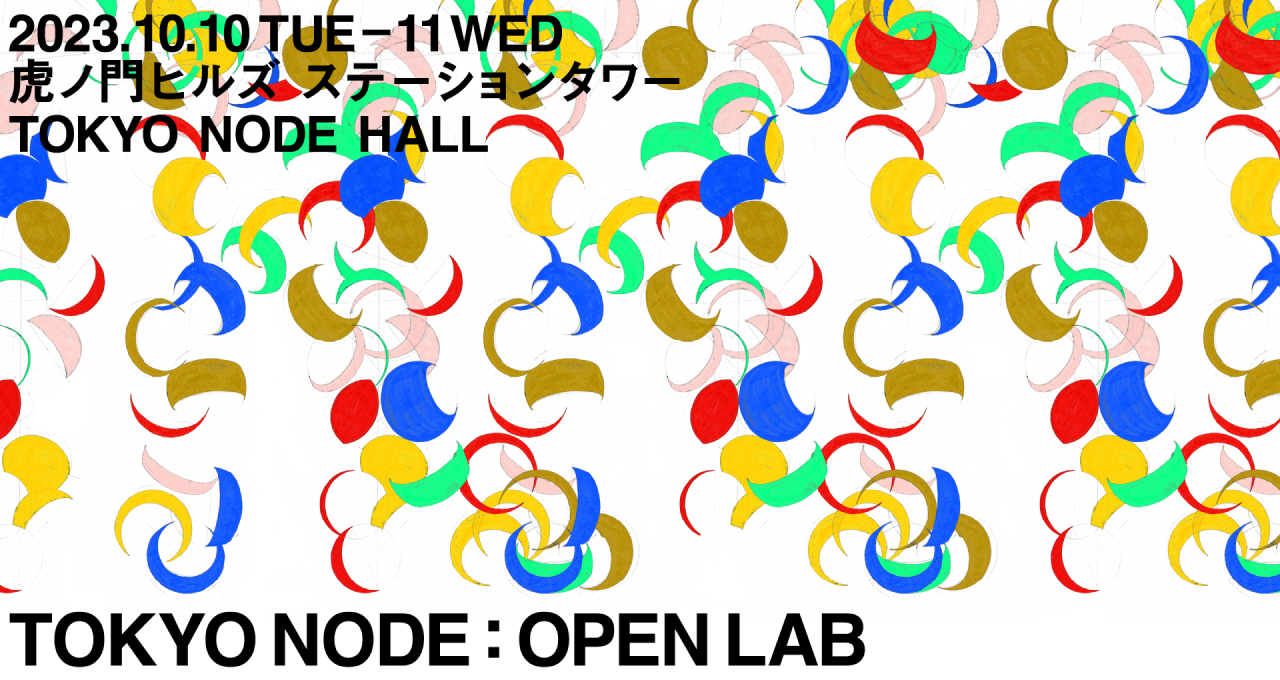「ハード」を駆動させる、新しい「ツール」が必要
「TOKYO NODE」がスペースを構える虎ノ門ヒルズ ステーションタワーの8Fにつくられた「TOKYO NODE LAB」。その名のとおりTOKYO NODEと連動するこのラボには、異なる領域の企業が20社近く参画しており、施設の中にはボリュメトリックビデオの撮影を行えるスタジオも併設されている。展示やイベントを行う施設がラボを構えることは珍しいことかもしれないが、その体制がTOKYO NODEをより個性豊かな施設にしていると言えるだろう。
「虎ノ門の未来を考えていくなかで、この街には新しいテクノロジーを生み出す力が必要だと感じていました。だからTOKYO NODEもホールのようなハードをつくるだけでは不十分だと思ったんです。この場所から新しい価値を生み出すためには施設を使いこなすための新しいツールが必要だし、そのためには専門的な技術や知恵をもったチームが必要ではないか、と」
構想段階からプロジェクトに携わっていた森ビル 新領域事業部の杉山央はそう語り、虎ノ門が世界へ新たな文化や情報を発信していく街になるためには、先端的なテクノロジーを扱える場やチームが必要だと考えていたことを明かす。そんなときに出会ったのが、現在ラボを牽引しているバスキュールの朴正義だった。以前からインターネットや都市、宇宙などさまざまなフィールドで活躍してきた朴と意見を交わすなかで、虎ノ門をリアルとデジタルの体験が入り交じる「ダイナミックデジタルツイン」の都市にするアイデアが生まれたのだと杉山は振り返る。